 コラム
コラム 子連れで「モネ 睡蓮のとき」を観てきました
京都市京セラ美術館で、2025年3月7日から6月8日まで開催中の「モネ 睡蓮のとき」を観てきました。 京都市京セラ美術館「モネ 睡蓮のとき」モネが大好き!というほどではない私と娘ですが(モネさんごめんなさい)、3月11日~3月28日は小中高...
 コラム
コラム  コラム
コラム 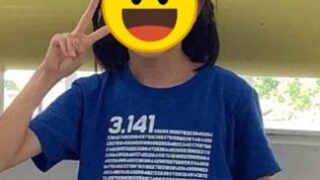 コラム
コラム  コラム
コラム 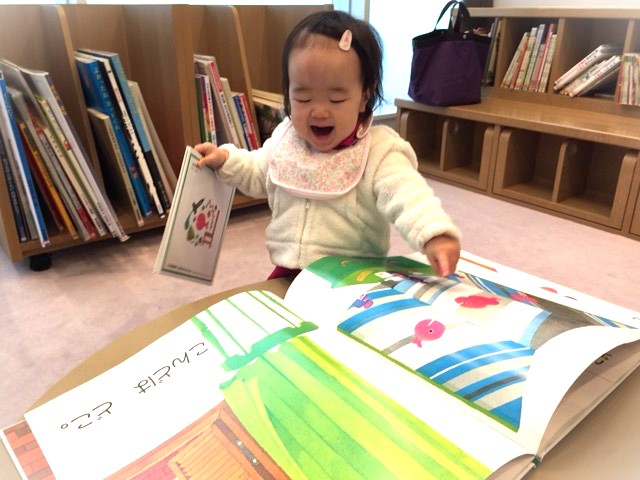 コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム 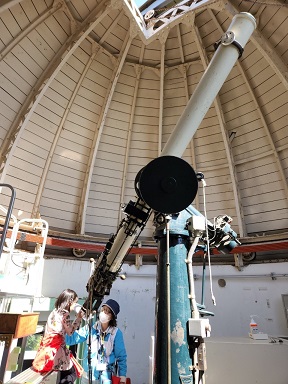 コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム